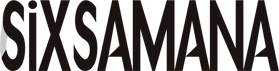クーロン黒沢のおもしろ沖縄探検記 沖縄の絶景廃墟:世界遺産と怪奇遺産【中城城跡】
沖縄南部、中城村にある城跡「中城城(なかぐすくじょう)」は、沖縄観光の中核をなす世界遺産である。
15世紀に活躍した琉球豪族「護佐丸」の拠点として築城され、江戸末期には浦賀に向かう途中のペリーがここに立ち寄り、石積みの城壁を絶賛したとも言われている。
戦争では沖縄にある城郭で唯一、致命的な破壊を免れ、今も中世の面影を色濃く残す貴重な遺跡として、内外に広くその名を知られている──そうな。
【クーロン黒沢のおもしろ沖縄探検記】 更新しました! 今回は沖縄の誇る世界遺産……の隣にある「不気味な廃墟」についてさらっと書きました。記事はリンク先から読んでね!